
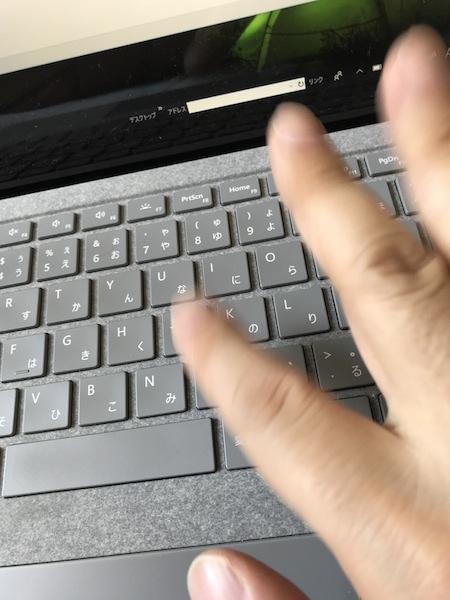
財務事務次官の醜悪なセクハラ問題は、さまざまな観点から論議が交わされている。そのうちここで記したいのは、被害者の女性記者が情報を「第三者」ーーすなわち『週刊新潮』に提供したのは「不適切」だったのか、という点。
これをことさら問題視する声は多く、大手メディアでは『読売新聞』が4月20日付朝刊の社説でこう書いている。
〈取材で得た情報は、自社の報道に使うのが大原則だ。データを外部に提供した記者の行為は報道倫理上、許されない〉
女性記者が所属するテレビ朝日も、当初はこの点を「不適切であり遺憾」と報道局長が会見で述べていた。ただ、その後に社長がやはり会見で「公益目的からセクハラ被害を訴えたもので、会社としても記者の考え、心情は理解できる」と語り、軌道修正している。
とはいえ、これはあくまでも「セクハラの被害者」として『週刊新潮』に告発したことを「理解」したものであり、記者としての情報提供まで容認したとは受け取れない。
では、記者が取材で得た情報を「第三者」に提供することは「不適切」なのか。もちろんここでは「第三者」を『週刊新潮』のような「他メディア」に限定して議論を進める。
一般論としては、決して適切とはいえないと私も思う。取材された者は通常、記者が所属するメディアで報道されることを前提としているからである。
しかし、これもまた建前的な原則論であり、すべての記者が「他メディア」に情報提供しなくなれば、私たちが多様な情報に触れる機会は激減し、この社会は相当に風通しが悪くなる。
具体的に考えてみよう。たとえば、月刊誌『文藝春秋』には「赤坂太郎」という筆者による連載がある。政界の生々しい動静や裏話を赤裸々につづり、長年にわたって続いてきた同誌の名物連載でもある。いうまでもなく「赤坂太郎」はペンネーム。大手メディアの政治部記者たちが代々、寄稿したり情報提供したりすることで成り立ってきた。
あるいは、会員制という形態を取る『選択』や『FACTA』といった雑誌もある。記事の大半は無署名だが、大手メディアではなかなか報じられないディープな情報がしばしば掲載され、私も愛読している。このうち『選択』は、次のような宣伝文句を古くから掲げてきた。
〈『選択』の編集には、国内外の400人を超える第一線のジャーナリスト、学者、作家、さらには政・財・官界人らが多数参加しています。『選択』はマスコミ界を横断する組織によって作られています〉
ここにある〈国内外の400人を超えるジャーナリスト〉には、大手メディアの記者が多数含まれている。いや、それがほとんどといってもいいのではないか。本サイトの編集長である久田将義くんも『選択』の編集者だった経験があるから、私よりもよく分かっていると思う(笑)。
かつて一世を風靡した月刊誌『噂の真相』などもそうだったし、ほかの多くのメディアも現場記者間の情報提供や情報交換によって成り立ってきた側面がある。かくいう私も、組織メディアに属していた時代、さまざまなメディアに情報を提供したり、記事を執筆したりしてきた。逆に、他メディアの記者や編集者から情報を提供され、特ダネ記事を書いたことだって幾度もあった。
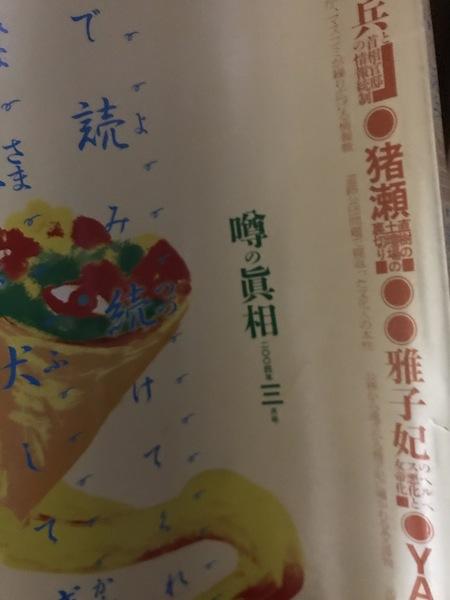
では、なぜこういうことが行われるのか。
残念な話ではあるが、それぞれのメディアには、それぞれのメディアの存立基盤や特性上、それぞれにタブー的な分野やテーマが存在する。取材先である当局や企業、大手芸能事務所、またはスポンサーや広告代理店との力関係のほか、記者クラブ制度などに由来する悪弊や所属メディアの社内事情などもある。そのようなものはすべてなくなるのがまさに理想ではあるし、タブーは打ち破るべく最大限の努力を尽くすのが重要なのは当然だが、現実にはなかなかに難しい。
そんな時、記者たちは他メディアに情報を提供する。もちろん、提供する際は取材源に不当な不利益や迷惑をかけぬよう配慮するべきだし、提供された側もそれを垂れ流しにするわけではなく、裏づけ取材を尽くす。なかには原稿料目当ての不届き者がいることを否定はしないが、他メディアに情報提供する多くの記者たちの心境はおそらく違う。
知り得た情報を、なんとか世に伝えたい。残念ながら所属メディアで伝えるのは難しくとも、他のメディアなら可能かもしれない。繰り返しになるが、それぞれのメディアにはそれぞれのしがらみがあり、こうしたことはしばしば起きる。それを一刀両断に「不適切」と封じてしまえば、情報自体が世に伝わらない。
それは今回のセクハラ問題をみても明白だろう。女性記者が『週刊新潮』に情報を提供しなければ、財務省トップのセクハラ問題そのものが表沙汰になることはなかった。
そういえば、〈データを外部に提供した記者の行為は報道倫理上、許されない〉と社説で書いた『読売』の記者から、私は何度か情報提供を受けて原稿を書いたことがある。貴重な情報を提供してくれた記者のうちの一人は、こんなふうに理由を明かして自嘲した。
「ウチは、トップが決めた社論に反するネタは書けないから」
もうひとつ、この論点をめぐっては、記者=ジャーナリストの独立性という問題もはらんでいる。たまたま特定のメディア組織に属してはいても、記者が本来奉仕すべきは、広い意味での読者や視聴者。記者たちがタブーなき核心情報を広く社会に伝えるためなら、組織の垣根を越え、もっと広く深くつながってもいい。個々の記者がもっとゲリラ的に動き回ってもいい。これを論じると長くなるので、また別の機会に書こう。
いずれにせよ、記者が他のメディアに情報を提供するのは必ずしも「不適切」ではない。(文◎青木理 連載『逆張りの思想』第六回)
【関連記事】
●森友問題・麻生太郎財務相の「謝罪会見」なのに謝罪する気、永遠のゼロ|青木理
●国際政治学者による「スリーパー・セル」「いま大阪ヤバい」発言は自戒せねばならぬ『野蛮な不寛容』|青木理
●「平昌五輪」に対する日本の立ち位置を考えてみた|青木理・連載『逆張りの思想』第三回











