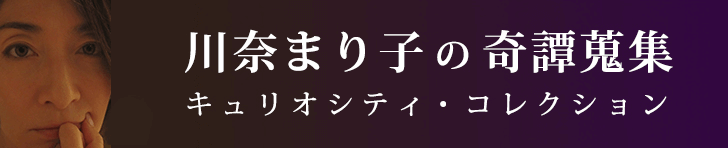

転勤族という言葉がある。企業や官公庁であちらの支部からこちらの支部へと頻繁に勤務先が変わる人を指す俗語だ。
朝井雪子さんの父親は或る種の公務員であり、転勤族だった。詳しくは書かないが、高度な専門知識と資格を要し、品行方正であることを世間から期待される仕事だったと述べておく。
雪子さんは富山県で生まれたが、一家は父が転勤するたび引っ越しを繰り返し、昭和63年(一九八八年)、雪子さんが13歳のときには東京都の新宿区に住んでいた。
その年、弟が生まれた。それまで朝井家には子供は雪子さんだけだったから、長男誕生ということになるが、その喜びを掻き消すような不幸が折しも朝井家を襲っていた。
雪子さんが物心ついたときから兆候があった父の酒乱と暴力が、母の妊娠中にエスカレートして、日増しに酷くなるばかりだったのだ。
家の中でどんなに荒れ狂っても、外では取り澄ましており、相変わらず周囲の尊敬を集める父だった。母も体面を気にしてどこにも救いを求めようとしなかったため、誰に知られることもなく、一家は急速に深刻な状況に陥った。
「今でもあの頃の荒れ果てた家のようすを憶えています。家具も壁も傷だらけでボロボロになり、カーテンがビリビリ裂けて短冊みたいに垂れ下がっていました。酔って帰ってきた父が、包丁を振り回して切り裂いたんです。物にあたるだけじゃなくて、父は私を殴ることもありました......」
弟が生まれると、ベビーベッドのそばが雪子さんの避難場所になった。赤ん坊の近くでは、父は暴力を振るわなかったのだ。
弟のベビーベッドはリビングルームに置かれていたから、雪子さんは家にいる間はできるだけリビングルームにいるようにした。
中秋の名月の頃のこと。
当時、弟は生後三カ月目に入り、雪子さんが微笑みかけると笑い返すようになった。生後三カ月というと、まだ首も座らず、よく「バブバブ」などと表現される喃語(なんご)も話さないが、表情が豊かになってくる時期だ。
夜の10時頃、いつものように雪子さんはリビングルームで学校の宿題をやっていた。弟は眠っており、母はベビーベッドの横でうつらうつらと船を漕いでいた。
と、そこへ、父が帰宅した。乱暴に床を踏み鳴らして真っ直ぐベビーベッドまでやってきて、いきなり赤ん坊を怒鳴りつけた。
「俺が帰ってきたのに、寝てんじゃねーよ!」
酒臭い息がプンと匂った。目を覚ました母が、咄嗟に弟を抱きあげる。急に抱っこされて弟が起きたのがわかり、雪子さんは「泣かないで!」と必死に念じた。酔った父が泣き声に苛立ったら何をするかわからない......。
「ところが、弟は泣きませんでした。その代わりに、母の腕の中から真っ直ぐに父の方を向いて、『あうあう』と声を発したんです。強い目つきで、眉間にシワを寄せて、『あうあう、あうあうあうあう』って怒っているみたいに」
最初、父は薄笑いを浮かべて、「なんだこいつ? 何か言いたいのか?」と弟の顔を覗き込んだ。
しかし、弟の怒気をはらんだ「あうあう」は止まなかった。
ついに、母が不安そうに、「どうしたの?」と赤ん坊に問いかけながら、父から視線を逸らさせようと体の向きを変えた。
すると弟は、首が座っていないはずの頭をぐるりと巡らせて父を睨みつけた。
そして尚も「あうあう」と言い続けた。
足もとから寒気が這い上ってくるように雪子さんは感じた。父も表情を凍りつかせたのがわかった。母は、「もうやめて!」と自ら抱いている弟に向かって叫んだ。
しかし赤ん坊は、「あうあう!」といっそう激しく"説教"をするばかりだった。
「亡くなったおじいちゃんの霊が、父にお説教するために降りてきたのだろうと後で母が言っていました。父をいさめられるのは父方の祖父だけでしたし、祖父は弟が生まれる少し前に亡くなって、当時私たちが住んでいた新宿区にお墓がありましたから。......父にも、自分を叱っているのが本当は誰なのか、わかったんじゃないでしょうか」
父はみるみる青ざめ、赤ん坊に向かってガバッと頭を下げたのだそうだ。
「ごめんなさい! ごめんなさい! もうしませんから許してください!」
この夜を境に、父の暴力は嘘のように止んだ。
"説教"を終えると弟はたちまち眠ってしまい、翌朝、雪子さんがベビーベッドを恐々覗き込んだときには、微笑むばかりでまだ何も喋れない、普通の赤ん坊に戻っていたのだという。(「説教する赤ん坊」|川奈まり子の奇譚蒐集・連載【四】)











