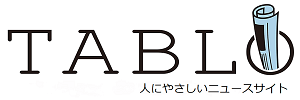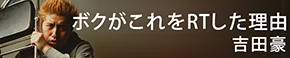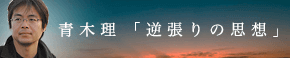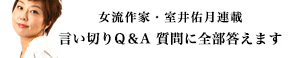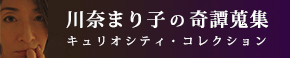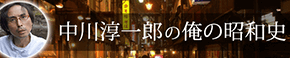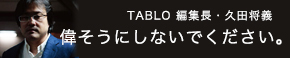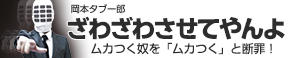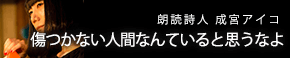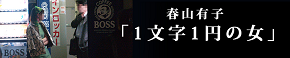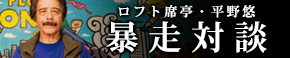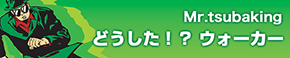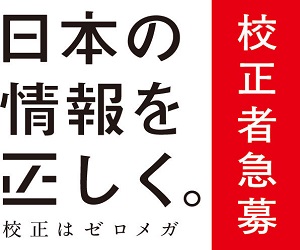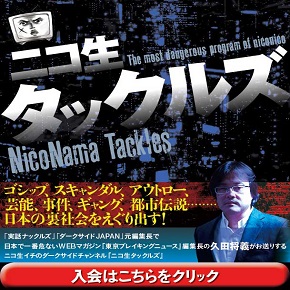まだある冤罪事件 真犯人は野放しに 名古屋高裁で無罪判決

福井県で、当時中学三年生の女性を殺害した疑いで逮捕・起訴され殺人罪で懲役7年が確定。前川彰司さんの再審が行われ、名古屋高裁は18日に無罪を言い渡しました。最高裁まで行くでしょうが、このまま無罪が通る見通しです。すなわち、えん罪で真犯人はまだ世に放たれている事になります。
警察・検察の大失態ですが、恐ろしい事でもあります。しかし、優秀だと言われている日本警察。なぜこのような冤罪を起こしてしまうのか。まだ以下のように冤罪事件は数々あるのです。
●足利事件(2010年・宇都宮地裁)群馬県で発生した幼女殺害事件で、当初の有罪判決後、DNA鑑定の誤りや共犯証言の不整合などが判明し、2010年に再審無罪が確定
●布川事件(2011年・水戸地裁) 強盗殺人事件で、被告が否認を続けたにもかかわらず複数の自白調書に基づいて有罪。再審で完全否認のまま無罪が確定 。
●東京電力OL殺人事件(2012年・東京高裁)東京電力社員女性殺害事件。鑑定結果の誤りと不自然な自白をもとに有罪判決。しかし2012年の再審で無罪が確定 。
●東住吉事件(2016年・大阪地裁)小学6年女児焼死事件。自白と不完全な証拠に過度に依存した有罪判決から、再審で無罪確定 。
●松橋事件(2019年・熊本地裁)再審開始に対し検察が即時抗告・特別抗告。最終的に再審無罪が確定。有罪立証の不備が指摘される 。
●湖東記念病院事件(2020年・大津地裁)医療現場での患者死亡事件。主要な証拠に疑義があり、再審で無罪が確定
●袴田事件(2024-2025年・静岡地裁) 1966年の一家殺害事件。死刑判決が確定後、長年にわたる再審請求を経て、2023–24年に無罪判決が確定。高齢化や証拠開示の遅れなど制度の問題点が浮き彫りに 。
●前川彰司さん事件(日野事件・愛知、岐阜関連) 群馬・岐阜の豊川幼児殺人事件に関し、自白調書を唯一の証拠とする起訴。再審請求段階に証拠開示が問題となり、制度改革の象徴的事例に 。
すべて再審無罪判決になっている事件は、自白調書を中心に、有罪を導く証拠の精査不足が共通点 です。証拠開示がにないか遅滞は再審開始の妨げになっており、多くの弁護士や被害者が法制度改革を訴えています。また検察による抗告権の濫用が、再審開始や公判の実現を引き延ばす要因となっていのも見逃せません。冤罪。これほど恐ろしい「罪」があるのでしょうか。(文@編集部)