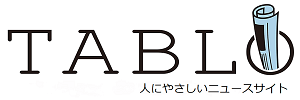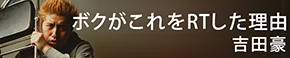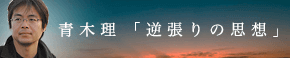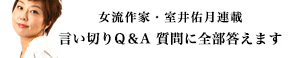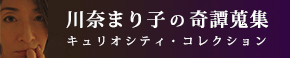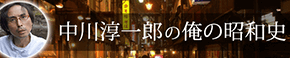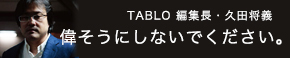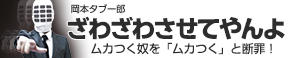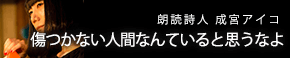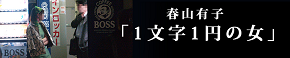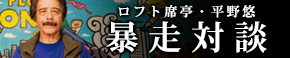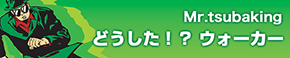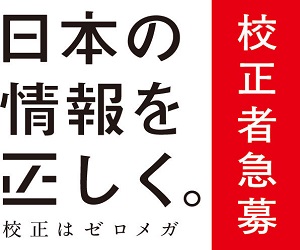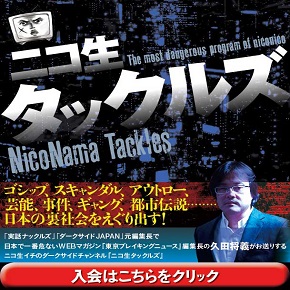陰謀論をバラエティチックな番組にしても大丈夫なのか

陰謀論を扱うテレビ番組や動画コンテンツの増加に伴い、それらが社会に与える影響についての懸念が高まっている。特にエンタメ性を重視した番組では、事実と推測の境界が曖昧になり、視聴者が誤った情報を真実として受け止めるリスクがある。
陰謀論の番組は、多くの場合、センセーショナルな演出や専門家のように見せかけた登場人物を用い、視聴者の興味を引くように構成されている。その過程で、根拠のない主張や検証されていない情報が繰り返し流されることで、視聴者の認知に影響を与えやすくなる。
このような番組の影響は、個人の思考だけでなく、社会全体の分断にもつながる可能性がある。特定の政治的立場や科学への不信感を助長する内容が含まれている場合、人々の間に誤解や対立が生まれ、公共の議論が建設的でなくなる。
また、陰謀論に基づく誤情報は、健康や安全に直結する問題でも深刻な影響を及ぼしかねない。例えば、ワクチンに関する根拠のない噂が広がれば、接種率が下がり、集団免疫の形成に支障が出ることもある。
視聴者にとっては、どの情報が信頼できるのかを見極めるリテラシーが求められているが、番組側にも制作の倫理が問われている。娯楽と情報の境界を明確にし、視聴者をミスリードしない責任がある。
陰謀論番組の拡大は、メディアの在り方や民主主義の健全性に対する警鐘とも言える。今後、情報の発信と受信の双方において、より慎重な姿勢が求められていくだろう。(文@編集部)