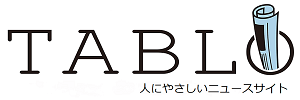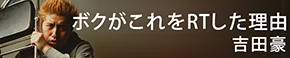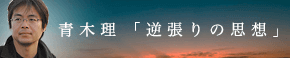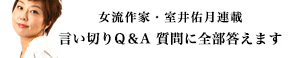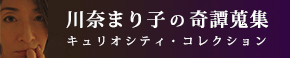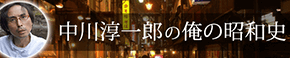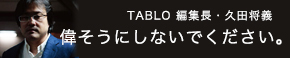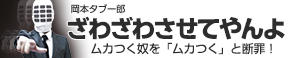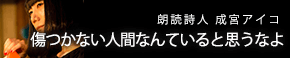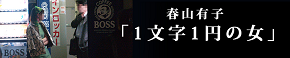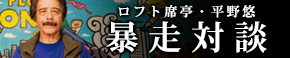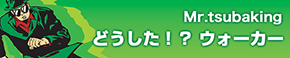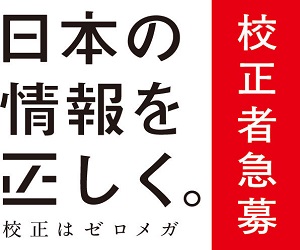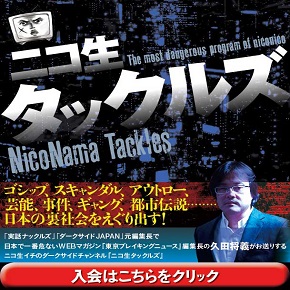歌舞伎町・大久保公園で立ちんぼ摘発 売春防止法とは何か

24日、新宿・大久保公園で 警視庁が4人の「立ちんぼ」女性を逮捕しました。容疑は売春防止法(売防法)。これによって、日本の風俗は一掃されたはずですが厳然として存在しています。この売防法施行の背景にはどのようなものがあったのでしょうか。
1950年代の日本は、戦後の混乱から徐々に社会が安定しつつあった一方で、都市部を中心に売春が公然と行われ、社会問題となっていました。とりわけ公娼制度の名残として、特定地域に「赤線地帯」が存在し、多くの女性が組織的に売春に従事していました。これに対して、戦後の新しい民主主義社会の価値観や、女性の人権を重視する国際的な風潮が高まり、旧来の制度や慣習に対する見直しが求められるようになっていきます。
1956年、そうした社会的背景のもとで「売春防止法」が成立し、翌1957年に施行されました。この法律は、売春を行う本人だけでなく、周囲でそれを助長・斡旋する者にも罰則を科すことを定めたものでした。ただし、売春そのものに対しては直接的な刑罰を設けず、代わりに「自立支援」や「保護処分」といった更生措置を重視する内容になっていた点が特徴的です。これは、売春を単なる犯罪として取り締まるのではなく、経済的困窮や家庭環境に起因する「やむを得ない行為」として捉え、社会全体での支援が必要であるという認識に基づいています。
売春防止法の施行により、公認の赤線地帯は廃止され、非合法化された売春は地下に潜ることとなりました。その結果、取り締まりは複雑化し、違法な形態での売春や人身取引の問題が新たに浮かび上がることになります。それでもこの法律は、日本社会が売春に対する姿勢を大きく転換した象徴的な法制度として、現在に至るまで一定の役割を果たし続けています。(文@編集部)