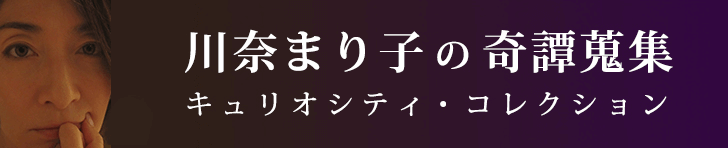
 写真はイメージです
写真はイメージです
高橋正さんは、秋田県八峰町にある神社の宮司一族の直系の血を引く。母方の曽祖父が宮司であり、男系の長子が家督を継ぐ慣例に従えば、宮司の長男である正さんの祖父が跡取りで、いずれは神主になったはずだった。
ところが正さんの祖父は神職を厭い、宮司の席を親戚に譲ったかと思うと、山にこもってマタギになってしまったのだという。
――私は、正さんから件の神社の名前を聞いて驚いた。
神宮や大社といった称号こそ冠されていないものの、有名な御社だったからだ。かつては修験道の霊場であり、不動尊を祀った境内に天然の滝を有することで知られ、年に一回ある滝浴びの行事は毎年マスコミで報じられている。
修験道が盛んに信仰されるようになった平安時代前期の853年、天台宗・比叡山延暦寺の第三代座主(住職)慈覚大師こと円仁が巡歴の折にこの滝を訪れて不動尊像を祀ったというのがその創建の由来だ。
中世の当時、日本の古神道と、新しく伝来した仏教の信仰とを融合する神仏習合のムーブメントが湧きおこった。その動きの中で、天台宗や真言宗といった密教(大乗仏教。円仁がいた天台宗の他に真言宗がある)に特有の修行と土着的な山岳信仰とが結びついて出来たのが修験道であり山伏である。
正さんの祖父は明治生まれだ。明治元年(1868年)の神仏分離令、そして明治5年の修験禁止令によって修験道が禁止され、廃仏毀釈によって修験道の山伏信仰に関わるものすべては廃棄された。修験道の時代を彼は知らないはずだ。
けれども、古い血に導かれるがごとく、近代神道に背を向けて、彼は山に入っていったわけである。
時は大正時代。代々宮司の家柄であればその地方の名家だろう。親に歯向かうにしても、マタギになるというのは良い家の跡取り坊ちゃんらしからぬ選択だ。
なにしろ、都会では洒落た洋装のモボやモガが闊歩し、自家用車と工業製品が普及しはじめていたのだから。いかに鄙びた秋田と言えども、今さら山でマタギになるより、里で一旗揚げるか学問の道に進む方が現実的だったのではあるまいか?
しかし彼は家族の意向にも時流にもことごとく逆らって、山へ......。
生来、岩が服を着たような無口な男で、他人と交わることを好まなかったのだという。彼は身体がきかなくなるまで、山でひたすら、猪や熊、鹿を狩り、鳥を撃った。あるいは海で鰰を釣った。そして獲物を妻子に食わせた。
彼の妻、つまり正さんの母方の祖母は、青森県出身の巫女だった。つまり彼ら夫婦は神社で知り合った。この出逢いが正さんの祖父に神職を捨てさせる原因になったのか否かは、もう誰にもわからない。
ともかく、彼女は、夫と違って社交的かつ現実的な性格だったようだ。子どもが生まれると現金収入を求めて村の給食センターに就職し、長年勤めた。
そして一家は、少々風変わりではあるが、山里の人々の暮らしに馴染み、村に溶け込んでいった。
しかし、彼らには特別な秘密があったのだ。
「もっこの話してらど、パカパカさんが来でさらわれっぞ」
正さんは、物心ついた頃から、こんなふうに祖母と母から二人がかりで度々強くいさめられた。
それは決まって、少し不可思議なものを見て、それについて家族に報告したあとだった。
祖母の出身地である青森県から秋田県や宮城県など東北地方で広く使われていた「もっこ」という方言は、幽霊や妖怪などの化け物全般を指す。
一説によれば「もっこ」の語源は「蒙古」で、約800年前の元寇のことだというが、本当のところはわからない。ともあれ、人ならぬモノたちを、正さんの祖母も母も、また、滅多に口をきかない祖父も「もっこ」と呼んでいた。
正さんには「もっこ」が見えた。
祖父、祖母、母も、見ることができるようだった。しかし、口外してはいけないのだということが、幼い頃の正さんには理解できなかった。
「だって、もっこだか何だかわかりませんが、それらが目の前にいるんですよ? 僕にもお母さんたちにも普通に見えているものなのに、それについて人に話してはいけないなんて、わけがわかりませんでした」
現在51歳の正さんは、ほとんど訛りのない標準語を話す。生まれたのは宮城県仙台市。そこの公営住宅に小学校低学年まで家族4人で住んでいた。
「弟がひとりいて、僕たちが小さな頃は、祖母が頻繁に訪ねてきました。また、僕と弟が祖父母の家に行くことも多かったのですが、もっこを見るたびに叱られるはめになって......。小さな子どもだから、お母さんやお祖母ちゃんに、どうしても話してしまうわけでしょう? すると、その都度、パカパカさんが来てさらわれるぞと、それはもう、きつぅく脅されました」
パカパカさんというのは、巨大な白い馬の形をした化け物なのだそうだ。
「祖父母と母は、そう言っていました。真っ白い大きな馬が蹄を鳴らして駆けてきて、さらっていくのだと......」
凶兆を知らせる白い馬
神社で馬と言えば、すぐに連想するのは絵馬と神馬。神馬の多くは葦毛(白)の馬だ。また、秋田や青森を含む東北地方にはかつて名馬の産地として知られていた場所が幾つもある。馬と人とが一つ屋根の下に暮らす「曲り屋」が広く見られたことでもわかるように、東北地方では古くから人の暮らしと馬が密接に関わってきた。そのせいか、馬にまつわる民話は多い。
今回は、私の探し方が悪かったのかもしれないが、「パカパカさん」のように白馬が子どもをさらう話は見つけられなかったが、岩手県遠野市の「おしらさま」伝説では、白馬の皮が娘を包んで天に舞い上がったきり戻ってこなくなる。それにまた、広い意味での白馬が登場する怖い伝説ならば、秋田県に伝わる「東山の小駒さん」や山形県の「岩野嶽山の白馬」がある。
秋田県の「東山の小駒さん」は、真夜中に一頭の白馬が蹄を鳴らして町を走り抜けた直後に大火事が起きて町が灰燼と化す事件があり、白馬は凶兆を知らせる神馬だったとして言い伝えられている話だ(鹿角市発行『鹿角市史民俗調査報告書第六集 花輪・尾去沢の民俗』鹿角市総務部市史編さん室・編)。
これと山形県の「岩野嶽山の白馬」も凶兆という点は類似しているが、こちらは知らせるのではなく、神通力で厄災をもたらした白馬の伝説だ。昔、岩野嶽山という山の御社・松尾明神の神馬が怒って山崩れを起こし、山裾の集落をことごとく埋め尽くし、数多の村人を死に至らしめて、飛び去っていったのだという(『にしかたの昔語り―村山葉山山麓の歴史と文化―』熊谷昇)。
――高橋正さんが聞いた「パカパカさん」は、あるいは彼の祖父母が創作したものかもしれない。しかし、そのルーツは東北地方に伝わる凶兆の神馬なのではないかと思うのだが、どうだろう?
では、正さんが見た「もっこ」の方は、どんなものだったかというと......。
「両腕をいっぱいに広げても抱えられないぐらいの大きな丸いものを、物心ついた頃からしょっちゅう見ていました。
色は灰色で、もやもやとした煙の塊みたいで、最初に見たのは4つになったばかりの頃。
幼稚園から帰ってきたら、箪笥の上にある2つのこけし人形がラグビーボールのような格好をした白いものに変身して、僕の方をめがけてフワーンと降りてきました。
すると、灰色の大きなボールみたいなものがどこからともなく現れて、その白い塊を2つとも、パクパクッと丸呑みにしたんですよ。
その後も何度か、こけしたちは白いラグビーボールのようなのになって箪笥から降りてきたけれど、毎回、灰色のやつが出てきて食べられていました。
また、当時はよく、玄関のドアやガラス窓から、毎日、昼となく夜となく、次々にいろんな人がヌルッと入ってきたものです。柔らかいゼリーを潜り抜けるような感じで、ヌルーッと知らないおじさんやおばさんが戸板やガラスの中から出てきて、家に入ってくるんですよ。みんな、顔や体に異常なところはなく、服も着ていて、生きた人間と全然見分けがつきませんでした。誰もかれも無表情で平然と侵入してきて、家の中を通っていこうとするのですが、これも片端から灰色のやつにパックンと食べられていました」
......という報告を幼い息子から受けた正さんの母は、
「もっこさ見だごど言うど、友だつが逃げでいぐがら、もっこの話はするんでね!」と叱りつけ、それでも正さんが黙らないとなると、「パカパカさんが来でさらわれっぞ!」と脅したのだそうだ。
祖母も同じで、「もっこが見えでも誰にも知られではなね! 話すとけやぐ(友だち)やお嫁さんが逃げでいぐはんで、けっすて言ってはいげねぇよ!」と厳しく孫を諭した。
祖父にも何か言われたが......。
「お祖父ちゃんの言葉はとてもきつい秋田訛りで、何を言っているのか僕にはさっぱりわかりませんでしたし、母ですらよくわからない始末で......。ときどき祖母が通訳していましたが、祖母が近くにいないときはお手上げでした。もっとも、祖父は滅多にしゃべりませんでしたけどね」
「もっこ」の本当の正体
祖父が灰色の「もっこ」について語っていたことを正さんが知ったのは、中2の夏休みだった。
その頃には祖父はマタギの仕事から引退し、神奈川県で母方の叔父(正さんの母の弟)の家族と同居していた。
小学生の頃からずっと、正さんは夏休みになると、仙台市の家に父を残して、母と弟と一緒に神奈川県の叔父たち一家を訪ねる習慣で、そのときも叔父の家に滞在していた。
中学生になっても正さんには「もっこ」たちが見えていたが、口外することはなくなっていた。しかし相変わらず、奇妙なものたちが出没しては、灰色の球に喰われていた。もう慣れっこになっていて少しも怖くないが、ほとんどの人たちにはこれが見えないのだと思うと、不思議な気がした。
ただ、中2のこのときまでは、「もっこ」が見える者は全員、同じものを見ているのだろうと思い込んでいた。
「でも、違ったんです。また大きな灰色の球が現れて、言うなと言われていたけれど、なぜかそのときは我慢できなくなった、祖父母に言ってしまったんですよ。すると、祖父が何か言って、それを聞いた祖母が僕にもわかるように説明してくれました」
「そいづは父っちゃさ神社の狛犬だ。おめは総領息子だはんで、護るだめに出でぎでらんだよ」
大きな灰色の球は、祖父が継ぐはずだった神社の狛犬だったのだ。祖父には、それが狛犬の姿に見えていたのである。
正さんはたいへん驚いたが、幼い頃、こけしが化身した白いものや戸板からヌルッと出てきた"人々"を、灰色の球が呑み込んでくれたことを思い出して、何か腑に落ちたように感じた。
あれらは悪いものたちだったのだろう。そして、これまでずっと自分は狛犬に守護されてきたのだ――と、納得がいったのだ。
祖母は連れ合いの通訳に一区切りつくと、正さんを台所に連れていった。コップに梅干しをポトンと落として、上から白湯を注ぎ、スプーンで砂糖をすくって中に入れると、くるくると溶き混ぜる。
「これば飲むともっこさいなぐなるんだ。前にも教えだが、よそのふとにはもっこのごどは言ってはいげね。お嫁さんがもらえねぐなってまるす、友だつにも気味悪がられっで縁ば切られるる。わがっだね?」
コップのものを飲むと、たしかに気分が落ち着いて、「もっこ」のことが気にならなくなった。祖母の言うように「いなぐなる」わけではなかったが。
正さんは、妻子にすら「もっこ」の話をしたことがないのだという。しかし、拙著を読んで、私には打ち明けられると思ったのだそうだ。
「本を読んで、この人なら話を聞いてくれると確信しました。これまでに大勢の話を聞いているでしょう? 僕の言うことも信じてもらえるんじゃないか、そしてお祖父ちゃんお祖母ちゃんの埋もれた話も、書いて、形にして残してもらえるんじゃないかと思ったんですよ」
狛犬は今もあなたのそばにいるのでしょうかとお訊ねしたところ、正さんは否定して、「30年ぐらい前から、存在が感じられなくなりました」と言った。
「就職するまでは、いつも自分の横か後ろに何かがいるような気がしていました。灰色の球も、十代の終わり頃まで、ときどき見えていました。でも会社に入ったら、いつの間にか......気がついたら消えていたんです」
正さんを護っていた神の使いは、秋田県八峰町の御社に帰っていったのだろうか。
かの山の御社には円仁によって見出された1100有余年前と変わらず、今も、冷澄な清水が滝を成している。山伏の姿こそ見当たらないが、ブナの原生林は森閑とし、滝の岩上には齢千年を超える不動尊が鎮座ましまし、鳥居の奥には灰色をした狛犬も侍りおる。
時を止めたかのような神域。そこから生まれた物語もまた、遠い昔の手ざわりを帯びていた。
――神主になるはずだったマタギと巫女。恐ろしい白い馬「パカパカさん」。さまざまな「もっこ」たちと守護の狛犬。
第六感を持つ一族――その末裔が、ある日突然、私の前に現れて語りだすとは! 夢でもみているような気分である。
実を言うと、正さんから聞いた話はこれで終わりではない。この続きは、いずれまた。(川奈まり子の奇譚蒐集・連載【十二】)
【関連記事】











