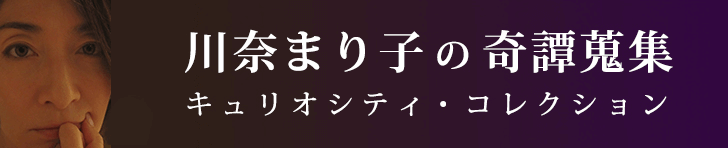
 高尾山薬王院の山門
高尾山薬王院の山門
川谷広樹さんは東京生まれの東京育ちだが、小学校にあがる前の一時期、八王子市に住んでいた。......いろいろご意見もあろうが、私自身、実家が八王子にあり、あそこがいかに東京らしくないかを知り抜いているので、こういう書き方をさせてもらう。
ともあれ、広樹さんは幼い頃に八王子に住んでいた。彼はひとりっ子で、体が弱かった。とくに持病があるわけではなく、なんとなくひ弱で、すぐに吐いたり熱を出したりするから幼稚園を休みがちで、お友だちができなかった。
おまけに物心ついてからというもの両親はずっと不和で、父は家に寄りつかず、さらに祖父母や親戚とも彼の母は疎遠だったから、母と二人っきりでアパートの部屋で過ごすことが多かった。
冬眠中の熊の親子のように、母子で巣穴に籠っていたようなものだ。広樹さんの世界は母と暮らす部屋の中だけで、ほぼ完結していた。
しかし、いよいよ夫と別れることになって、彼の母には何か思うところが生じたのだろうか―――突然、虚弱な我が子の手を引いて、高尾山薬王院にお参りすることにした。
広樹さんは5歳だったが、このときの参拝は七五三とは関係がなかった。高尾山薬王院といえばお正月の初詣に何万人も押し寄せることで知られているが、秋口の出来事だからそれでもない。
よく晴れた、爽やかな日和だった。暑くもなく、寒くもない。朝食後、家を出発して、母と二人、電車に揺られて行った。
八王子市の高尾山薬王院は、その名が示す通り、高尾山という山にある。川崎大師(神奈川県川崎市)や成田山(千葉県成田市)と並ぶ真言宗智山派の関東三大本山のひとつだけれど、広樹さんによれば彼の母はべつに信心深かったわけではないとのことだから、ごく素朴な気持ちから、近場の参拝地としてここを選んだのだろう。
狭い巣穴からいきなり外に連れ出された広樹さんには、高尾山で目に映ったものすべてが新鮮で、少し怖かったようだ。
参道の傾斜路も境内の階段も、体が丈夫ではない5歳児にとっては、苦行を強いる恐ろしい場所だったはずだ。
もちろん、二人は休み休み、ゆっくりと山を登っていった。
また、ご存じない方のために説明すると、高尾山の開発の歴史は古く、山麓から山の中腹まではケーブルカーかリフトで登るのが昔から一般的だ。広樹さんより20歳も年上の私が幼児の頃、すでに高尾山でケーブルカーやリフトに乗っていたぐらいだ(※)。どちらも終点付近では眼下の地面との高低差が200メートル以上になって眺望が素晴らしいので人気があるのだ。
無数の天狗像に足がすくむ
――絶景を見晴らしながら、広樹さんの小さな手を、母はたびたび強く握ったそうだ。繋いだ手を離すまいとしたのは、他の観光客、参拝客の中で迷子になることを恐れたためだけだったろうか?
広樹さんは、と言うと、こんなに高い所に登るのは生まれて初めてで、山の上から眺める景色に見惚れたかと思えば足をすくませたり、山を訪れている大勢の人々に呆然としたりと、心が慌ただしく揺れ動いて落ち着く暇がなかった。
薬王院の山門を潜るまでの彼の記憶は曖昧だが、私に話してくれた断片的な小エピソードを繋ぎ合わせると、おそらくケーブルカーで母子は山門のある山の中腹まで登った。
そこから薬王院の御本社までは、大人の足なら30分程度の距離だ。
しかし何しろ虚弱体質の5歳児を連れているので、通常の倍以上の時間がかかったようだ。朝から登りだしたのに、山門前の権現茶屋に辿りついたのは昼過ぎになってしまったらしい。
夕暮れ前に帰宅しようと思うなら、もう、あまりのんびりしていられない感じだ。昼飯を食べ終わると、二人はすぐに御本社に向かった。

ところが、広樹さんは山門を潜るのを最初は拒んだ。
そこにある一対の仁王像が怖かったのだという。
彼の母は、泣いて抵抗する広樹さんをなんとかなだめて一緒に山門を潜った。だが、境内のそこかしこにある天狗像が、また、広樹さんには恐ろしく感じられた。あいにくと高尾山には天狗伝説が数多くあり、薬王院には天狗像がこれでもかというぐらい建てられているのだ。
仁王像も怖い。天狗像も怖くてしかたがない。
怯え切っていたところ、彼は一個の石と、彼の言い方を借りるなら、「目が合った」。地面に敷かれた砂利の中から、その小石は泣きつかれた彼の眼を真っ直ぐに見つめているようだったという。
このときの感動を広樹さんの言葉で綴ろうと思う。
「綺麗な石で、周りの石ころとは全然違って、輝いていました。だから僕は、お母さんの指輪のように、この石は宝物だと思ったんです。表面は滑らかで、半分白くて半分は黒く、鶏の卵より少し小さくて、握りしめると僕の掌にぴったり納まりました。目の前にかざしてクルクルと回して見つめたり、握りしめたりしていると、なんだかとても楽しくて、嬉しかった」
――お母さんの指輪のように。
玩具がわりに、彼の母は息子にときどき大事な指輪を貸してやっていた。でも、その指輪が母にとって唯一の宝物だということを、幼心に広樹さんは理解していたのである。
母は、息子が手に持っている物にすぐに気がついた。
「境内の中の物は全部、《神さま》の物なんだから、元の場所に返しなさい」
広樹さんは言うことを聞かなかった。そのときの彼にとっては、この石だけが心の安寧をもたらす唯一の物だったからだ。
おっかない天狗像。帰るときにまた見るのかと思っただけで緊張してしまう、阿吽の仁王像。目も眩む高みからの景色。見知らぬ人、人、人......。
それに一体、なぜ、いきなり高尾山に連れてこられたのか。いつもと違う母の行動も、幼い彼には怖かったに違いないのだ。
綺麗な白黒の小石を、境内にいる間じゅう、彼はかたくなに左手で握りしめていた。お参りも右手だけでやりすごす意固地さを見て哀れに思ったか、山門を出るまで、母はもう彼を叱らなかった。
そして母子は山門を抜けて、参道への階段を下りた。
お母さん、僕の手が!
階段を下りたとき、広樹さんは石を握っていた左手に違和感を覚えた。
ヌルッとしてきて、石が掌の中で滑るような気がしたのだ。
そこで掌を開いて見てみたところ、鉄くさい臭いがプンとして、掌といい指といい、一面に真っ赤な液体で濡れていた。なぜか痛くなかったが、これはどう見ても血だ。
「お母さん! 僕の手が真っ赤なの! 見て! こんなになっちゃったの!」
大声を出して掌を母に突き出すと、母はしげしげと眺めて、「そこの水道で洗おうね」と彼を参道の脇の手洗い場に連れていった。
洗うとたちまち赤い液体は流れて取れた。掌には、まったく傷がついていなかった。また、持っていた小石の方は、洗ってもいないのに、なぜか赤い液体が付着していなかったのだという。
「ずっと後になって、このときの出来事について母と話したところ、母には赤い液体が最初から見えていなかったことがわかりました。僕を安心させるために、手を洗わせたんだそうです。でも、僕は未だにはっきりと思い出せるんです。手が血塗れになっているようすが......。本当に驚きました。神さまに見られていたのだと、あのときは信じたし、今でもそう思います」
石は拾った場所に置いてきた。赤く濡れていた掌は、その後は何も変わったことはなかった。
ほどなく母と父は離婚して、広樹さんは母と一緒に23区内へ引っ越した。彼はそれから十年ばかり、母と共に都内を転々とした。
――思うに、《神さま》は、その日からずっと二人を見守っていたのではなかろうか。
貧しさと苦労はつきまとったけれども、広樹さんはめきめきと丈夫になった。私が会ったときの彼は頑健そうな青年で、彼の母もご健在だという。
奇妙な出来事をその後も何度か彼は体験したそうだ。しかし、それは、高尾山薬王院で出逢った《神さま》が時折ようすを見に来ていただけかもしれないと思う。《神さま》の正体が天狗なのか真言宗智山派の始祖・弘法大師空海なのかなんて野暮な推理はしないでおこう。(川奈まり子の奇譚蒐集・連載【十三】)











