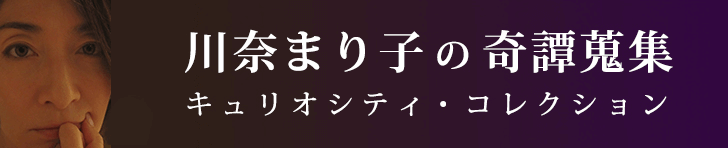
 写真はイメージです
写真はイメージです
決まった土地や建物に現れる霊が地縛霊と呼ばれることは、今日ではよく知られている。朝里樹の『日本現代怪異事典』によると、地縛霊という言葉が現在と同じ意味で使われるようになったのは1970年代以降のオカルトブームの頃だと推論されている。
しかしながら特定の場所に出るオバケの逸話は、もっとずっと古い時代から存在するようだ。
たとえば、江戸時代に書かれた根岸肥前守鎮衛の奇譚拾遺集『耳嚢』の巻之九には、「怪倉の事」という以下のような逸話がある。
――本所(現在の東京都墨田区の南半分)に屋敷を構えている数原という幕府のお抱え医師の蔵に、古来より如何にも恐ろしい僧形の化け物が居ついていて、蔵の物を出し入れするのに、これにいちいち事前に報告しておかないと非常に良くないことが起こるとされていた。
数原家ではこの決まりを律儀に守っていたが、あるとき近所の火事が延焼して屋敷が焼けてしまった。寝泊まりする所を失った数原家の家来が、例の蔵は無事だったので、そこで寝ようと思いつき、化け物に断らずに物を片づけて寝床をつくって休んでいたところ、言い伝えどおりに坊主の化け物が現れて、
「昔からの決め事を破って無断で蔵に入ったうえに、なんと無礼にもここで寝るとは憎らしい。本来なら命を取るべきところだが、こんな非常時であるがゆえ、今回だけは許してやる。以後、決して立ち入らないようにせよ!」(※)
と、脅しつけた。家来は慌てて逃げ出し、それから数原家では毎年欠かさず蔵の化け物を祀り、決め事を守っている――。
自分のテリトリーに入ってきてほしくないなら、さっさと祟り殺してしまえばよさそうなものを、お互いに妥協し合えるラインを決めるあたり、なかなか紳士的な化け物だと思う。
......どうしてこの話を思い起こしたかというと、これには理由があって、今回ご紹介しようと思っている体験談に登場する地縛霊めいたオバケも、住人にちょっとだけ妥協してくれるタイプなのだ。
体験者さんの話を聞いて、オバケがもう少し寛容だったらよかったのにと気の毒になったが、オバケの方が先住者なので、人が遠慮するのが筋というものかもしれない。
驚くほどにボロい家
大分県在住の岡村正博さんは22歳の頃、腰の骨が疲労骨折する脊椎分離症という厄介な病気になって外科手術を受け、年をまたいで4ヶ月も入院した。
入院している間にそれまでいた宮崎県の社宅を追い出されてしまい、2月に退院すると同時に、愛媛県の支所に臨時的に異動させられた。
そこで5月まで、3ヶ月だけ働いたら大分県の本社に呼び戻すし、宮崎県で臨時に住まう家も用意すると約束してもらったので喜んで辞令に従った次第だが、行ってみたらその家というのがとてつもないボロ家で驚いた。
戦前に建てたと思しき小さな二階家で、なんと1階の玄関と炊事場は茶色い土が剥き出しになった土間。壁は土壁。2階へ上がる階段はハシゴをやや斜めにしたような段梯子で、恐ろしく急勾配。トイレは一応、家の中にあるものの杉板で蓋をする〝穴〟で水も流れない、ボットン便所のラスボスの如き代物。
ガスと電気は来ていたが、台所で煮炊きをするなと引っ越しに立ち会った支所長から厳命が下ったので、うかつにガスを使うと爆発するのかもしれなかった。
電気の方も尋常ではなく、まず、壁にプラグ受けが一個もない。梁からぶらさがったり、壁の穴から伸びたりしている電気コードに電球のソケットやコンセントが直接接続されていたから、家が建てられてだいぶ経った後に強引に文明開化したことが推察できた。
さらに、窓の数が少なかった。1階には、玄関の引き戸の擦りガラスと炊事場とトイレの小窓の他は窓が無い。
荷物を運び込む前に家の周囲を廻ってみたら、2階に4枚引きの掃き出し窓が認められ、これがこの家で唯一の窓らしい窓なのだった。掃き出し窓の外に傾いた物干し台が設けられ、窓の雨戸は開いていた。支所長か不動産屋が開けておいてくれたのだろうと岡村さんは思った。
この家について、岡村さんが愛媛の支所長に聞いたところでは、何年も、ひょっとすると何十年も閉め切ったまま、必要最小限の管理しかされてこなかったらしいとのことで、引っ越した日には、前述したように時代錯誤な造りとボロさ、不便さに加えて、屋内にこもっていた悪臭にも衝撃を受けた。
腐った野菜に埃っぽさと汗臭さを加えたような、饐えた臭い。
玄関で回れ右して大分の実家に帰りたくなってしまったが、支所長は、この家以外はどうしても用意できないのだと岡村さんに告げた。おまけに、畳替えを含む一切の改装をなぜか禁じた。
「たった3ヶ月の辛抱じゃないか。ここで我慢してくれ。岡村くんが頼りなんだ」
支所長が彼を頼りにするのは道理で、この愛媛の支所には元々、所員が3人しかいなかったのに、内1人が足を骨折して休職してしまったので、仕事が回らなくなっていたのだ。
3ヶ月というのは、休職中の所員の怪我が治癒するまでの見込み期間というわけだった。支所長は彼にこんなことも言った。
「岡村くんも4ヶ月も入院していたそうじゃないか? きみが休んでいる間は誰かがその分、苦労したんだ。今度はきみが頑張る番だよ。わかるよね?」
文句を言ったらクビになってしまうに違いないと、岡村さんはそのとき悟った。
この家は1LDK で、1階と2階にそれぞれ6畳が1間あり、当初、岡村さんは2階を寝室にしようと考えていた。
しかし、引っ越し作業を開始して、段梯子を下から眺めてみたら2階が真っ暗で、上っていったら闇に吸い込まれてしまいそうな気がして怖くなった。
また、腰はまだ本調子ではなく、こんな垂直に近い段梯子を上り下りしないで済むなら、それに越したことはないとも思った。
――暗くて怖いし、腰もアレだ。2階は放置で!
岡村さんは、そそくさと階段の下を離れて、1階の6畳間を出来る範囲で心地よく整えることに決めた。
ささくれだった古畳に木綿のラグを敷き、オーディオセット、テレビ、小型の電気ストーブ、ベッド、テーブルといった現代的な生活に必要なものを配置した。
6畳にこれだけ詰め込むと通路しか残らないが、致し方なかった。
そして、夜になった。
ベッドに横たわる......と、天井からギィギィキシキシと床板が軋むような音が降ってきた。
家鳴りだろうと思った。
一般に、夜は気温が下がって湿度が上がる。すると古い木造家屋では木材や鉄釘が膨張または収縮して音が鳴る。これがいわゆる家鳴りで、妖怪の仕業や心霊現象に因るラップ音ではないのだ。
以前、どこかで読んだ知識を思い返して、不安にならないように岡村さんは努めた。そしてその晩は引っ越し作業で疲れていたので、ほどなく眠りに落ちたのだった。
翌日、夜の7時頃に支所から帰宅すると、家の中から人々が囁き合う声が聞こえた。玄関の土間で立ちすくみ、おっかなびっくり首を伸ばして6畳間の方を覗き込んだら、土壁が青い光を照り返していた。
テレビが点いていて、囁き合う声と思ったのはテレビの音声なのだとすぐに理解したが、出掛ける前に電源を切ったはずなのでおかしい。
また、ボリュームも、自分が調節したときより音量が下げられているのが奇妙だった。
不思議だけれど、深く気にしないようにしようと強いて努め、チャンネルを自分の好みに合わせて音量を上げた。
その途端、昨夜と同じ、家鳴りがしはじめた。天井の方々がギィギィキシキシと盛んに鳴る。
こんなことが毎晩続いた。
およそ1ヶ月が経った頃の日曜日の午前、岡村さんはコーヒーがいっぱいに入ったマグカップをテーブルで引っくり返してしまった。たちまちコーヒーがテーブルの端から滴り落ち、ラグに大きなシミを作った。
木綿のラグだから洗濯機で洗える。咄嗟の判断で、岡村さんはラグを畳から引っぺがし、洗濯機に放り込んでスイッチを入れた。
乾燥機能付きの洗濯機だったらよかった。もしくは乾燥機を持っていたら。
洗ってしまってから後悔しても遅かった。
それまで洗濯物は小さなスタンド式のタオル掛けやハンガーに吊るして1階の6畳間に干して乾かしていたのである。
ラグは大きすぎる。困ったと思ったが、すぐに2階の物干し場が頭に浮かんだ。
濡れたラグを抱えて、昼でも暗い階段を初めて上った。
上がると半畳ほどのスペースを挟んで正面に襖紙を貼った片開きの扉があった。普通のドアノブの代わりに鉄の把手が付いている。押し開けると、キィーッと実に不気味な音を立てて開いた。
開くと同時に、人の汗と脂が古くなったような、鼻が曲がりそうな悪臭が押し寄せた。何の臭いだろう。咄嗟に室内を見回した。
一方の壁に近い畳に大きな黒いシミがある。それ以外は何にもない六畳の部屋だった。シミは小柄な人ぐらいの大きさで、よくわからない形をしていたので、真っ先に雨漏りを疑ったが、天井板にはそれらしい跡は無かった。
正面に4枚引きのガラス窓があり、物干し台が見えた。
ラグを抱え直して、岡村さんは畳の上に一歩、踏み出した。
ギィ......と足の裏で聞き覚えがある音がした。
――いやいや、まさか、違うだろ。夜に鳴るあれは家鳴りだろうよ。
ゾッとしかけたのを打ち消しながら、窓の方へ歩み寄ったのだが。
ギィギィ、キシキシ、ギィギィ、キシキシッ!
間違いなく、毎晩聞いている音。それが一歩ごとに足もとで鳴った。
全身の毛が逆立って、一気に血が下がった。慌てて踵を返して扉の方を向いた瞬間、背後で彼を脅すようにひときわ大きく、ギィッと鳴った。
後ろには誰もいないはず。......いや、誰かいるのか?
戸口で凍りつき、恐々と振り向きかけたが、再びギィギィと後ろで床が鳴ったので急いで段梯子の方へ向き直って、あとはもう、転げ落ちるように駆け下りた。
するとすぐに頭の上から、キィーッと、これまた聞き憶えがある音が落ちてきて、辺りの影が濃くなった。
上の部屋の扉が閉まったのだ。
岡村さんは湿ったラグを抱きかかえたまま、財布とキーホルダーだけ持って家の外に逃げ出した。
オバケからの「要求」
自家用車なしでは暮らせない田舎のこと、岡村さんも自分の車を持っていた。ボロ家に似つかわしい雑草だらけの横の空き地は、かつては庭だったのかもしれないが、今は駐車場代わりとなっている。
車に飛び乗るまで、家の中から射るような視線を向けられている感じがしていた。シートが濡れるのも構わず、ラグを後部座席に放り込んで、彼はとりあえず出発した。
あてどなく走りはじめ、しばらく車を転がすうちに、少しずつ気持ちが落ち着いてきた。冷静さを取り戻すと、駅前の市街地へ行けば必ずやコインランドリーがあるだろうと思いついた。
――初めからこうすればよかった。最初からコインランドリーを探しにいけば、怖い思いをしないでも済んだのに。
コインランドリーの後すぐに帰宅する気になれなくて、その日、岡村さんは街で夜まで時間を潰した。
ようするに日中から飲み歩いたわけである。彼は前から酒好きで、引っ越してきてからは人とのふれあいに飢えてもいた。
何軒目かわからないスナックで可愛い女性と知り合いになり、彼女と別れてから、酔い冷ましのために車の中で2時間ばかり仮眠した。
深夜、帰宅して、慌ただしく入浴と着替えを済ませると、すぐに頭から布団を被って寝直した。
例の音が聞こえないように、両手で耳をふさいで目を閉じていたのだが、眠りに落ちる寸前で尿意を催してしまった。
おっかなびっくり布団から頭を出して枕もとの目覚まし時計を確認したら、午前1時。
ベッドに入る前に豆球を点けておいたから、部屋はセピア色に明るんでいる。耳を澄ますと、好運なことに、今はしんと静まり返っていた。
岡村さんは急いでトイレに立った。粗末な板壁と杉板の戸に囲まれたボットン便所に入り、天井から下がった剥き出しの電球にスイッチを入れて後ろ手に戸を閉めた。掛け金を掛けて、おもむろに便器に向き直って、小便をした。
出すべきものをすっかり出し終えた、ちょうどそのとき。
ギィギィキシキシ、ギィギィキシキシ......キィーッ!
2階から、あの音が聞こえてきた。誰かが歩いて、戸を開けて、そして、
ミシッ!
放出しきったはずの小水が、なぜか少量飛び出してきて、便槽に落ちていった。恐怖のあまり漏らしたのである。震える手でパンツとパジャマのズボンを引き上げてトイレの戸に耳を押し当てると、また、ミシッ......と。
何者かが段梯子を下りてきたとしか思えなかった。
足音はさらに、ミシッミシッと続き、そして突然、便所の灯りが一瞬明滅したと思ったら、パチッと音を立てて消えた。
臭くて真っ暗な箱に閉じ込められてしまった。もう震えが止まらない。
――ごめんなさいごめんなさいごめんなさい! もう2階には行かないから許してください!
頭の中で必死に謝っていると、トイレの戸が外から勢いよく叩かれた。
バーン!
悲鳴をあげて戸から離れ、さらに懸命に「ごめんなさい」と心で唱えつづけた。
何分経ったかわからないが、しばらくして段梯子を上る足音が耳に届き、次いで2階の戸がキィーッと軋みながら閉じられたのがわかった。
その翌日から、時を問わずにあの音がするようになった。
朝、テレビを点けるとギィッ!
帰ってきて、ステレオの音量を上げてCDを掛けはじめるとギィギィッ。
入浴中に歌っていたら、歌声を打ち消すようにギィギィキシキシ喧しく鳴った。
そして彼が帰ってくると、留守中にテレビやラジオが点けられて、点けっぱなしになっているのだが、いつも必ず、音量がとても小さかった。
あるとき、掃除機を倒して大きな音を立てたら、ドン!と2階の床を踏み鳴らされた。
――音で僕を威圧している! もしかして、静かにしろと言いたいのか?
考えてみれば、向こうが先に住んでいたところへ、人間の都合でこちらが押し掛けたわけである。オバケにしてみれば、いい迷惑だろう。
2階には決して行かないこと。なるべく音を立てないこと。オバケが求める条件がこの2つだけなら、呑もうじゃないか――。
岡村さんは、オーディオ機器を楽しむときはヘッドフォンやイヤフォンを使うようにし、日常、あまり音を立てないように気をつけはじめた。
その結果、ギィギィいう音が明らかに減った。
面白いもので、岡村さんは、いったんオバケの存在を認めてしまうと、ラジオやテレビが勝手に点けられていても平気になったのだという。
お互い様だと彼は思った。オバケの方でも機嫌を直したようで、もう滅多に怪音で脅してこない。互いに妥協し合えるようになったのだ、と。
しかし、このオバケとの蜜月は、残念なことにそう長くは続かなかった。
それは、1本の電話から始まった。(つづく)
※川奈による現代語訳。原文は『耳嚢(下)』岩波文庫版p.222~223を参照のこと。
後編へ続く:オバケの棲む家(後編) 「オバケと真っ向から闘った男の運命は」|川奈まり子の奇譚蒐集十九
【関連記事】
●子どもたちの前に現れた『キューピッドさん』からのメッセージ|川奈まり子の奇譚蒐集十七
●『霊は"見える人"へ寄り付いてくる』 不動明王を信心する母に育てられた男|川奈まり子の奇譚蒐集十六











